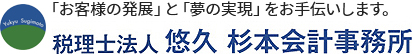減価償却資産に関わる特例
はじめに
企業が持つ資産には、時間の経過とともに価値が減少していくものがあります。そのため、資産の購入にかかる費用を一度に経費として計上するのではなく、年数をかけて少しずつ経費化する「減価償却」という仕組みが導入されています。この減価償却は、企業の税負担を軽減し、経営資源の有効活用を促進するための重要な手段です。
本コラムでは、減価償却の基本的な考え方と、特例について詳しく解説していきます。
1減価償却資産
事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産のように、一般的に時の経過等によってその価値が減っていく資産を減価償却資産といいます。
このような減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものと考えられており、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続を減価償却といいます。
しかし、使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
2原則
取得価額が10万円以上のものは固定資産として計上し、減価償却を行う場合は、原則として、その取得価額を品目ごとに定められている耐用年数で毎期に分けて計上します。
しかし、減価償却資産の減価償却には一定の要件を満たした場合、特例処理を行うことが
が認められています。
3一括償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
4少額減価償却資産
一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(一括償却資産の適用を受けるものを除きます。)については、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。なお、令和4年4月1日以後に取得などする場合は、少額減価償却資産から貸付け(主要な事業として行われるものは除きます。)の用に供したものが除かれます。
5注意点
一括償却資産には上限額がないことに対して、少額減価償却資産の特例には年間で300万円までという制限があることには注意が必要です。また、少額減価償却資産の特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要な点についても把握しておかなければいけません。
おわりに
減価償却資産の特例制度を理解し、自社の状況に応じて適切に活用することは、税負担の軽減や資金繰りの改善に直結します。特例適用に伴う要件や手続きを正確に把握し、必要な対策を講じることで、より効果的な資産管理と税務対策を実現しましょう。
参考:
国税庁
「No.2100 減価償却のあらまし」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
企業第二課 監査担当 東 寛太郎